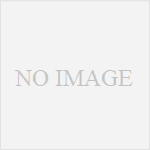私は深川の門前仲町生まれだが、私の父も門前仲町で生まれ育った。
父は東京大空襲のときにまさに東京・深川にいた人である。
当時の本所区、向島区、深川区、城東区(現在の墨田区、江東区)は壊滅的にやられたが、
まさにその渦中に父はいた。
その時の話を、私は子供頃に何度も聞かされた。
父の父(私から見れば祖父)はその当時、お金持ちだったらしい。
門前仲町一帯の土地を持ち、工場を持ち、商売を拡張していた。
父の七五三の写真などをみると、すんごい衣装を着ている。
当時、本当にお金があったのだなぁというのが伝わってくる。
祖父は私が生まれる前にとうに亡くなっていたので、私は会ったことがない。
しかし父から祖父の話を聞く限り、なんだかとても勘の強い人だな、と思う。
東京大空襲があった前日、祖父は何か予感でもしたのか、
父の母(私からみると祖母)と父の妹たちを疎開させた。
東京には祖父と父が残った。
大空襲がおきる朝、祖父はさらに何か予感でもしたのか、
自分の家にあった全財産をカメにいれて、庭の一角に埋めた。
祖父は幼い父に
「お前、この上からおしっこをかけて置け」といって、
おしっこをさせたらしい。
そして
「これでよし」と言ったという。
とつぜん空襲は始まった。
父と祖父は逃げた。
火の粉が舞うなか、大勢の人が一方方向に流れていく。
否応なくそちらに逃げていく父と祖父だが、祖父はふと立ち止まって言ったという。
「正男、そっちへ行ってはいけない。そっちへ行ったら死ぬぞ。あっちへ行くんだ。」
人の流れに逆らって、逆へ逆へと祖父と父は走り出した。
そしてその先は火の海だった。
「あの向こうへ行くんだ。」
一刻の躊躇もせずに祖父は父の手をとって、火の海の中に飛び込んだという。
その時に火の粉が防災ずきんに燃え移り、父は酷いやけどを負った。
その火傷の後は死ぬまであった。
命からがら、火の海を越え、休める場所にたどり着いた。
そこへ座った瞬間、父は眠ってしまったという。
その時に父は臨死体験をした。
臨死体験の話は、私は幼いころに何度も聞かされた。
「気がついたら雲の上のようなところにいて、なんとも気持ちがよかった。
由美、人は死んだらあんなところへ行くんだよ。」
あの世に行きかけたところで、
いきなり祖父が「寝るな!!!!!」怒鳴って
頭からバケツ一杯の水をぶっかけたという。
祖父は父があの世に行きかけたのを察知したのだろう。
バケツ一杯の水を頭からかけられた父は寒くて寒くて凍えるようだったという。
朝になって、自分の家があった場所へ行ってみた。
一面焼け野原である。
隅田川は死体でいっぱいだった。
火を逃れて川で死ぬ人がいっぱいいたらしい。
父はその時、川辺にいた丸焦げの人が、
口だけあいてパクパク息を吸っているのをみたという。
死体は一面にあったが、なぜかその死体だけがとても印象的だったらしく、
その光景が脳裏に焼き付いて離れない、と言っていた。
祖父の言ったことは正しかったという。
あの時、人が流れて行った方向に行ったら、確実に死んでいたらしい。
そちらは死体の山だった。
自分の家も丸焼けだったが、庭に埋めたカメは無事だった。
多くの人がパニックになる中、祖父はものすごく冷静だったのだろうな、と思う。
祖父は戦後大変苦労した。
戦争で全ての財産を没収されてしまったからである。
祖父の持っていた工場も土地も国に奪われた。
それでもまた戦後に一から事業を立て直し、
亡くなる頃にはまたひと財産を築いていたらしい。
しかし働きすぎた。頑張りすぎた祖父は早死にした。
具合が悪くなった祖父を父は一生懸命看病したという。
祖父は
「調子がいい時はみんなやってきて、飲んだり食べたりしにくるが、ひとたび調子が悪くなると誰も来ない。人とはそんなものだな。」
とよくよく言っていたという。
その祖父は父が高校生の時に亡くなった。
私の父は長男だったが家を継ぐ気はなかった。
勉強して大学へ行って、会社の社長になるのだという野望を抱いていた。
さすが山羊座男である。
父は戦争の時からそう思っていたらしい。
学校で先生に将来何になりたいかを一人ずつ言わせる場面があった。
まわりの同級生たちは「将校になりたいです!」「海軍に入りたいです!」という時代。
父は「会社の社長になりたいです。」と答えたという。
すると先生は
「お前は、みんながお国のために働いているというのに、会社の社長になって金儲けするのか!」
といって怒鳴りつけたという。
そのことを父はずっと根にもっているようだった。私に何度も言ってたから。
父はその後長い年月をかけながら、自分の夢を切り開いていった。
会社の社長にもなった。
外資系の会社の日本支社の社長にもなり、
時に話題となり、雑誌や新聞にも載った。
たぶん、父の希望どおりではなかったかもしれないが、
それでも父は日本と海外をまたいで、
果敢にビジネス展開していたと思う。
父が亡くなる前、私に言っていた。
「まぁ、もうちょっとやりたかったけどね。でも、まぁ、こんなものかな。」
父はまるでドラマのように母の腕のなかで
「ありがとう、ありがとう」と言って死んだ。
家のベットで母に、ご飯を食べるのを手伝ってもらいながら、
最後にごくごくと水と沢山のんで、
そのまま、ありがとうと言って死んだ。
私はこんなに上手く死ぬなんてずるいとさえ思ったほど、
父は上手に死んだ。
私は一つ後悔していることがある。
父が体調がすぐれない時、どうしたらいいか、と私に電話してきた。
色々話を聞いて、私はうっかり言ってしまった。
「しょうがないよ。人は必ずいつか死ぬんだよ。」
そういってしまった後、電話の向こうで父が息をのんで固まったのがわかった。
一瞬の沈黙・・・・・
「そうだよな。」といった父の声が震えていた。
私はしまったことを言ってしまったと思った。
老いること、生きること、死ぬこと、
いつもわたしたちは命がけだ。
夏になると不思議に父のことばかり思う。
お盆というのはやはりそういう季節なのだろう。